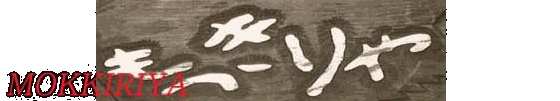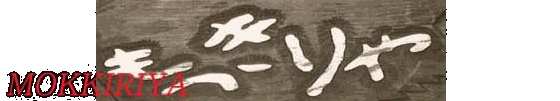|
2015/04/14(火)
山の暮らしはさびしかないか
|

|
|
朝からくもって、霧だか雨だかわからないような重い風が立っている。
なんとなく薄さむい感じがして、こんな時こそ室内で遊んでいるしかない。僕の読む小説は時代物が多くなってその中の記述にはよくブラブラ病という病が出てくる。部屋のなかから外の重い風景を伺っているとどうも自分もそんな患者になったのだろうかと思うこともある。どうも根が真面目なのだろうか。あんまり真面目だという奴はろくなことにはならないのだけれど。そう、だからこんな山のなかで逼塞しているのだ。
「島流し」という刑罰があって宇喜多秀家は関が原の後、家康に八丈島に流された。その秀家の唯一の喜びは家康の死後も八丈で生き延びたことだったと読んだことがある。また「山流し」という処分もあったという。これは旗本などの武士が虚けて遊んでばかりいると「甲府勤番」に配置換えをさせられることだという。お江戸の賑わいから放されて甲州の山周りは爛熟した江戸の面白さから遠ざけられ真っ暗な寂しい暮らしはまったく「山流し」と感じられたのは当然だったのだろう。となると僕のここでの暮らし向きも「山流し」かというとそんなことはない。今はここから見れば吉原も島原も指呼の間で、成田を辿ればパリもニューヨークもひとっ飛びだからだ。
|
 |
|
|